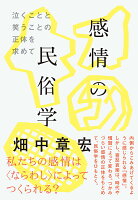フェミニスト経済学
- 『フェミニスト経済学 : 経済社会をジェンダーでとらえる』
- 有斐閣
- 2023.10
- ISBN: 9784641166202
- 出典:国立国会図書館書誌データ(2025年7月31日取得)
-- フェミニスト経済学 | 楽天ブックスフェミニズムの視点から,すべての人のウェルビーイングの実現をめざす。 日本ではじめてのフェミニスト経済学のテキスト! 第1部 理論と方法 第1章 フェミニスト経済学への招待 第2章 アンペイドワーク──人間のニーズとケア 第3章 世帯──世帯内意思決定と資源配分 第4章 生活時間──資源としての時間 第5章 ジェンダー統計──社会を把握するツール 第2部 領域と可能性 第6章 労働市場──ペイドワ …