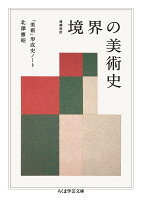「家庭」の誕生
- 『「家庭」の誕生 : 理想と現実の歴史を追う』
- 筑摩書房
- 2023.11
- ISBN: 9784480075901
- ちくま新書 ; 1760
- 出典:国立国会図書館書誌データ(2026年1月28日取得)
-- 「家庭」の誕生 | 楽天ブックスイエ、家族、夫婦、Home・・・・・・。様々な呼び方をされるそれらをめぐる錯綜する議論を追うことで、これまで語られなかった近代日本の一面に光をあてる。 イエ、家族、夫婦、子ども、ホーム、ファミリー、 これらを語る際、避けては通れない歴史がある。 内側から問う日本の近現代 イエ、家族、ホーム、ファミリーなど、多くの名が生まれた理由は、その言葉を用いないと表現できない現象や思いがあったためだ。「家庭」 …