リサーチのはじめかた

- 『リサーチのはじめかた : 「きみの問い」を見つけ、育て、伝える方法』
- 筑摩書房
- 2023.8
- ISBN: 9784480837257
- 出典:国立国会図書館書誌データ(2025年4月11日取得)
-- リサーチのはじめかた | 楽天ブックス最もむずかしいのは、リサーチをはじめる前の段階だ。スタンフォード大教授らが18年かけて磨きあげた、「きみの問い」が見つかるリサーチの極意。読書猿氏推薦!

-- リサーチのはじめかた | 楽天ブックス最もむずかしいのは、リサーチをはじめる前の段階だ。スタンフォード大教授らが18年かけて磨きあげた、「きみの問い」が見つかるリサーチの極意。読書猿氏推薦!

-- アフォーダンス(9) | 楽天ブックスJ・J・ギブソン発案の最重要概念であるアフォーダンス。その実相や可能性について心理学の歴史を遡ることで辿り、神経科学との接点をも探る。さらには対人関係や社会制度における社会的アフォーダンスを論じ、「流体の存在論」へといたる、シン・アフォーダンスの書。 序(田中彰吾) 1 ビリヤード台としての自然 2 生命から始める 3 本書の構成 第1章 心の科学史から見たアフォーダンス(田中彰吾) 1 知覚をど …
-- 高校野球の制度研究 デュルケーム理論からみた社会学的分析 | 楽天ブックス
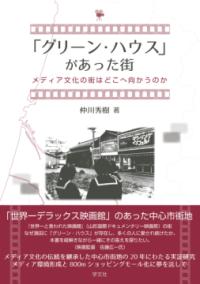
-- 「グリーン・ハウス」があった街 | 楽天ブックス『世界一と言われた映画館』(山形国際ドキュメンタリー映画祭)の街。 なぜ酒田に「グリーン・ハウス」が存在し、多くの人に愛され続けたか。 本書を紐解きながら一緒にその答えを探りたい。(映画監督 佐藤広一氏) 「世界一デラックス映画館」のあった中心市街地メディア文化の伝統を継承した 中心市街地の20年にわたる実証研究。メディア環境形成と800mショッピングモール化に夢を託して。
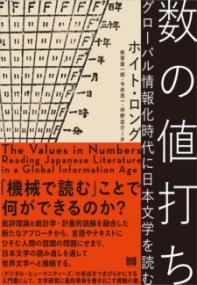
-- 数の値打ち | 楽天ブックス「機械で読む」ことで何ができるのか? デジタル・ヒューマニティーズ×日本文学研究から 生まれた驚くべき成果。 デジタル時代の文学リテラシーがこの一冊で つかめる、最前線の研究をいち早く翻訳! 数字と文学のあいだの概念上の分断を超えて、批評理論と統計学・計量的読解を融合した新たなアプローチから、 言語やテキストにひそむ人間の認識の問題にせまり、日本文学の読み直しを試みる。 データ・サイエンスの影響を …

-- ジェンダー格差 | 楽天ブックス第46回サントリー学芸賞作(政治・経済部門) 歴史・文化・社会的に形成される男女の差異=ジェンダー。その差別は近年強い批判の対象だ。 本書は、実証経済学の研究から就業・教育・政治・解消後の可能性について、国際的視点から描く。 議員の女性枠導入=クオータ制が、質の低下より無能な男性議員排除に繋がる、女性への規範が弱い国ほど高学歴女性が出産するエビデンスなどを提示。旧来の慣習や制度について考える。 【 …

-- 改訂新版 コーヒーと日本人の文化誌 | 楽天ブックス日本で最初の喫茶店「可否茶館(かひさかん)」が開店したのは、政治や社会、都市が大きく変貌を遂げつつあった明治の中頃、1888年のことである。コーヒー自体は、それよりさらに200年ほど前にすでに日本に伝わっており(薬としても)飲まれていたようだが、コーヒーを近代的な都市生活の中に取り込み、人びとの日々の暮らしと文化の拠り所として定着させたのは、「可否茶館」の創業者である鄭永慶(ていえいけい)だと言わ …
-- 入門 精神医学の歴史 | 楽天ブックス古代から現代まで、各時代におけるパラダイム、治療の場や「狂気」の概念、そして患者の生活に触れつつ、精神医学の歴史を概説する。 第1章 古代ーー自然現象としての狂気、文化事象としての狂気 第2章 中世ーー「頭の病気」 第3章 ルネサンスーー病院の中のメランコリー 第4章 バロックと啓蒙主義ーー癲狂院と神経病患者 第5章 19世紀の精神医学ーー保安、治療、研究 第6章 20世紀ーーバイオサイコソーシャ …

-- コミュニティを研究する | 楽天ブックス街づくりやコミュニティデザイン、プレイスメイキングなどが注目され、地域を基盤とした住環境の改善、生活の質の向上を目的とした活動が展開されている。そのときに不可欠な近隣地域やコミュニティの測定法を体系的にわかりやすく解説した本邦初の本。 監訳者まえがき / まえがき / 謝辞 第1章 はじめに コミュニティおよび近隣地域を定義する 本書における測定手法の全体像と測定法の包含基準 測定の信頼性 測定の …
-- 「うらみ」の心理学的特徴の検討 | 楽天ブックス「うらみ」が一般にどのようなストーキングを動機づけるのかなど、さまざまな視点やデータから「うらみ」の心理学的特徴を検討。
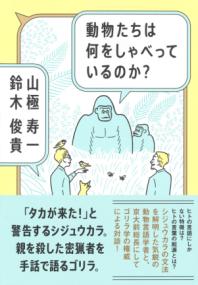
-- 動物たちは何をしゃべっているのか? | 楽天ブックスつい最近まで、動物には複雑な思考はないとされ、研究もほとんどされてこなかった。 ところが近年、動物の認知やコミュニケーションに関する研究が進むと、驚くべきことが分かってきた。 例えば、小鳥のシジュウカラは仲間にウソをついてエサを得るそうだ。ほかにも、サバンナモンキーは、見つけた天敵によって異なる鳴き声を発して警告を促すという。 動物たちは何を考え、どんなおしゃべりをしているのか? シジュウカラにな …
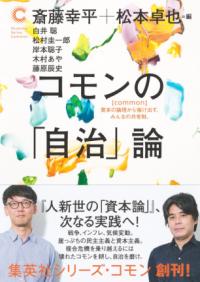
-- コモンの「自治」論 | 楽天ブックス【『人新世の「資本論」』、次なる実践へ! 斎藤幸平、渾身のプロジェクト】 戦争、インフレ、気候変動。資本主義がもたらした環境危機や経済格差で「人新世」の複合危機が始まった。 国々も人々も、生存をかけて過剰に競争をし、そのせいでさらに分断が拡がっている。 崖っぷちの資本主義と民主主義。 この危機を乗り越えるには、破壊された「コモン」(共有財・公共財)を再生し、その管理に市民が参画していくなかで、「自 …